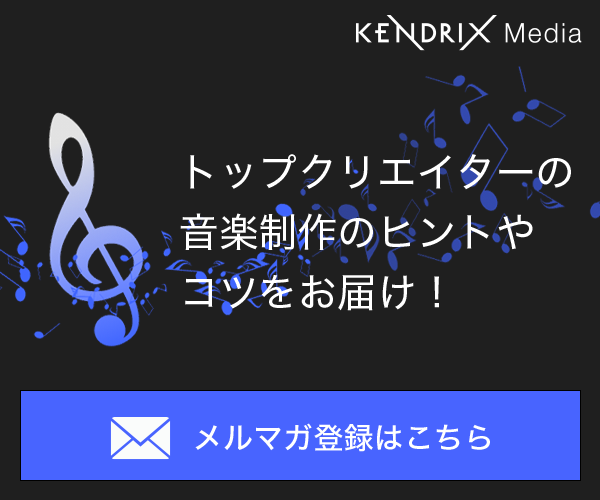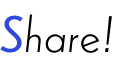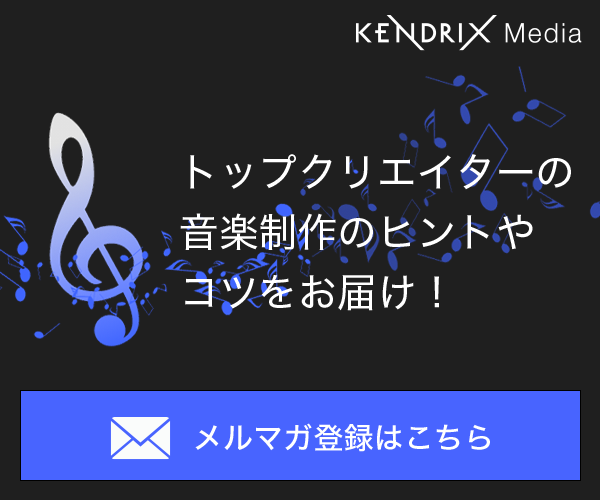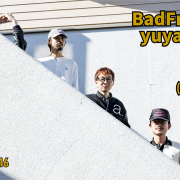ミュージシャンの職業病「ジストニア」とは?予防法を古屋晋一さんに聞く

ミュージシャンの職業病である「ジストニア」をご存じでしょうか。
身体が意図しない動きをしてしまうこの病気に悩まされる演奏家は少なくありません。
予防方法から最新の練習方法まで、ミュージシャンの体の使い方を専門家である古屋晋一さんに伺いました。
古屋晋一さんプロフィール
株式会社ソニーコンピュータサイエンス研究所 東京リサーチ リサーチディレクター
2002年大阪大学 基礎工学部卒業後、同大学大学院 人間科学研究科、医学系研究科を経て、2008年に博士(医学)を取得。
主なピアノ演奏歴として、KOBE国際音楽コンクール入賞、日本クラシック音楽コンクール全国大会入選、Ernet Bloch音楽祭出演、兵庫県立美術館ソロリサイタルなど。
1日4時間以上の反復練習をすると「ジストニア」にかかるリスクが高まる

――普段はどういう研究をされているのでしょうか。
身体を効率的に使って、思い描いた演奏を生み出す方法を研究しています。
上達するための練習方法のほか、怪我を防ぐ方法も調べています。
――スポーツ選手の怪我と違い、ミュージシャンの怪我が話題にあがることはまだまだ少ないです。
そうですね。私自身がピアノの演奏で手を痛めてしまったことから、この研究を始めたのです。
ドイツから日本に帰国した2014年頃も、まったく注目されていない領域でした。
10年ほど啓発活動を続け、ようやく広がってきています。
――ミュージシャンに多い怪我にはどういうものがありますか。
よく言われるのは腱鞘炎です。腱が痛んだり、炎症を起こしたりすることで痛みが出る疾患です。
ピアニストを対象にした調査では、200名のうち66%が過去に痛みやしびれを経験したことがあると出ており、それが重症化した腱鞘炎は、ミュージシャンの発症率が非常に高い怪我ですね。
他に、私が主に研究している「ジストニア」という疾患もあります。
身体が意図しない動きをしてしまう疾患で、「サックスを吹くと首が勝手に動いてしまう」「声帯や舌が固まって声が出なくなってしまう」などの症状が出ます。
――演奏家にとっては致命的な症状ですね。どんな原因でなるのでしょうか?
速くて正確な動きを繰り返していると発症しやすいです。
力を使ったり、疲れたりしない練習でも、正確性を意識して繰り返しているとかかりやすいですね。
――練習時間の長さと関係はありますか。
1日4時間を超えると発症率があがると報告されています。
――音大生やプロのミュージシャンならすぐに超えてしまいそうな時間です。
そうなのです。練習時間を減らすのは現実的ではないので、練習内容で予防することが重要です。
同じ動きを繰り返すことが発症につながるので、リズムを変える、力の加減を変える、別の曲をはさむといった形で、多様な練習をするのが有効です。
それから休憩を取ることも重要ですね。休憩中も脳は学習しているので、何時間も休まず練習するのではなく、適宜休憩を入れるスケジュールを計画的に組むのもひとつの方法です。
正確に同じテンポ・リズムを刻む音楽ジャンルは発症しやすい
――どういう楽器を演奏しているミュージシャンに多いのでしょうか。
ギター、ピアノ、バイオリンなど、速く正確な動きをする楽器であれば、楽器の種類は問わないですね。
ただ、発症する部位は楽器によって違います。サックスなどは口や首、フルートは手指、ピアノは右手に発症しやすいです。
一番酷使するところに出やすいということですね。
――性別・年齢・人種などで発症しやすさに差はあるのでしょうか。
まず挙げられるのは遺伝的なリスクです。血液検査はできるのですが、重篤でない限りは検査まで至らないことが多く、本人は気づいていないことが多いですね。
それから性格面もあります。神経質な方、完璧主義な方が発症しやすいとされています。
また、性別については、楽器全般について研究されているわけではなく、よくわかっていません。

――発症しやすい音楽ジャンルがあればお聞きしたいです。
クラシック音楽はテンポやリズムが大きく可変ではないことが多いので、発症率が高いです。
逆に、ジャズなど即興演奏やリズムがよく変わるジャンルは発症率が低いですね。
ファンが「完璧な演奏がある」と考えないことが大事
――日本ではまだ注目されていない領域だというお話がありましたが、海外ではどうでしょうか。
病気や治療法といった医学の領域でもっとも進んでいるのはドイツです。演奏者の姿勢などの教育はアメリカとイギリスが進んでいますね。
一番遅れているのは日本を含めたアジアです。
国際的に活躍するアジアの演奏家は増えているのに、彼らのサポートが他国より遅れているのが喫緊の課題だと思っています。
我々の研究所が行っているピアノアカデミーでは、ジュニア向けの怪我の予防法や練習方法を教えています。
クセがつかないうちから予防するのが重要ですね。
――すでにクセがついている人が予防したい場合、どういう方法がありますか。
例えば、我々のピアノアカデミーでは、カメラを使ったセンサーシステムで、クセの原因を分析する方法をとっています。
これまでも、鏡を置いて自分のフォームを見直すという練習方法はありました。
しかし、どの瞬間にどこを見ればいいのか、どのフォームが正しいかは解剖学などの知識が必要でした。
我々の場合は、アプリで動きを可視化して、悪いフォームのときはアラートを出したり、容易に身体の異常を知ることができます。
こうしたカメラやアプリを使ったフォームの改善は、スポーツの世界では当たり前ですが音楽の世界ではまだまだです。
アーティスト側の啓発もふくめて、取り組んでいく必要があると思っています。

――アーティストのケガを防ぐために、ファンが知っておくべきこと、心得ておくべきことがあればお聞きしたいです。
ふたつあり、一つめは「完璧な演奏があると考えないこと」です。
録音編集技術が進んだことにより、音や映像で完璧な演奏にふれることに慣れて、わずかなミスに過敏になってしまうことがあります。
アーティストにストレスを与えないためにも、視聴者には、生の演奏にはミスがつきものだと思って聴いて欲しいですね。
二つめは「ネットに簡単にネガティブな感想を書かないこと」です。
SNSが普及したことでリスナーの反応がすぐに見えて、それがアーティストのメンタルに強い影響を与えるようになりました。
メンタルの不調は怪我にもつながりやすいので、アーティストに見られていることを意識した視点を発信する際に持たれると良いと思います。
緊張をほぐすためのVR練習
――古屋さんは怪我の予防のほか、人前での緊張をほぐす方法も研究しているとお聞きしています。まず、緊張することでどんなデメリットがありますか。
まず、指・口・舌などの動きが不正確になってしまうという影響があります。
もうひとつは、記憶へのアクセスが難しくなり、覚えたことを思い出しにくくなります。人前でスピーチの内容を忘れることがあるのも緊張の影響です。
最後が、音に過敏に反応してしまうということです。
自分が鳴らそうとしている音と違う音を拾ってしまう、その音に演奏が過剰に引っ張られてしまう、といった悪影響があります。

――緊張をほぐす方法もお聞きしたいです。
人が緊張するのは「レアな環境で、成功したら大きなご褒美が得られる状況」のときです。
ご褒美の方を変えることはできないので、我々は「レアな環境」を変える方法に取り組んでいます。
具体的には、VRでコンサートなどの本番環境を再現して慣れてもらうという練習方法を提供しています。
VR以外にも、友達などに聴いてもらい、本番に近い環境をたくさん経験するのも有効ですね。
それから他の方法でよく知られているのは「自分が抱えている緊張やストレスを紙に書いたり、スマートフォンに打ち込む」という方法ですね。
緊張していることに向き合い、紙などに書き出すことで緊張をほぐすことができます。
地道な練習ではなく創造性のために時間を使うのが未来の音楽練習
――最後に、古屋さんが取り組んでいるロボットを使った練習方法について教えてください。
指にはめて使う楽器練習用のロボットを開発しています。先に演奏する曲を設定して、あとは指を入れるだけですね。
ピアノ経験者が30分ほどこのロボットを使うと、その後、指をより速く動かせるようになります。
練習せずに上達するので、怪我を防ぐ方法のひとつになります。そのほか、いまの練習方法で頭打ちになった人の限界突破にもなると考えています。
ピアノがないときに練習できること、体が動きを覚えて暗譜の助けになる得ることもメリットですね。

――まさに夢のような機械ですね!
ただ、普及するためにはアーティストの意識改革が必要だと考えています。
日本では、1日4時間練習すると褒められますが、海外では「なぜ4時間もかけたのか」といわれます。
一般的にアジア圏は地道な努力、つらい努力を称賛するカルチャーがあるので、こうしたテクノロジーを使った新しい練習方法は受け容れられにくいことがあります。
しかし、音楽はスポーツと違って指をとにかく速く動かせればいいわけではありません。むしろそれは表現方法のひとつで、重要なことは「なにを表現するか」です。
例えば「薬指を巧みに動かすためだけに練習時間を使う」というのは、アーティストにとってもったいないことだと思うのです。
テクノロジーで地道な努力の時間を短縮し、自分ならではの表現をつきつめる、創造性の向上により時間をかける。
それが、これからの音楽練習のスタンダードになっていくと考えています。
――大変おもしろいです。今後の研究や活動の目標について教えてください。
アーティストむけに身体の使い方を教えるトレーニングセンターを作るのが、我々が目指しているところです。
スポーツでは当たり前のこうした設備を演奏者向けに提供し、研究成果を教育に実装してく仕組みを提供していきたいです。
――本日はありがとうございました!
TEXT:まいしろ

(プロフィール)
エンタメ分析家。データ分析やインタビューを通して、なんでもないことを真剣に調べてみた記事をたくさん書いてます。音楽と映画が特に好き!
X:https://x.com/_maishilo_
note:https://note.com/maishilo
PHOTO:和田貴光

Ex
おとログ
怪我・病気
テクノロジー
分配率届
ファッション
タイアップ
音源類似チェック
タンバリン
打楽器
Soneium
Breaking Atoms
メディア
インタビュー
クリエイタープロフィール
MAKE J-POP WITH
写真
カメラ
サイン
ゲーム音楽
ビートメイカー
声優
ASMR
ボカロP
IPI
ISWC
筋トレ
防音
シンガーソングライター
...and music
旅
KENDRIX EXPERIENCE
1of1
ヒップホップ
ロック
グランドライツ
ミュージカル
ジャズ
ダブ
FLAC
eKYC
ケン&ドリーの音楽の権利とお金の話
撮影
フェス
ロゴ
デザイン
ジャケット
カバー
マネタイズ
心理学
フィギュアスケート
振付
実演
ライブハウス
PA
音響
アップデート
作品登録
共同著作者
音響効果
映画
プロデュース
ギター
MC
音質
アイドル
音楽ができるまでをのぞいてみた
存在証明
信託契約
保護期間
取分
団体名義
兼業
副業
広告
カタログ
WELCOME TO THE PYRAMID
K-POP
J-POP
曲名
音楽メディア3万円お買い物!!
ソフト
CD
CM
DAW
DJ
MV
NFT
TikTok
YouTube
アニメ
アレンジ
イベント
グッズ
コライト
サンプリング
データラボ
バンド
フィンガープリント
ブロックチェーン
プロデューサー
プロモーション
ボーカル
ミュージシャン
ライブ
リミックス
リリック
レコーディング
作曲
作詞
劇伴
実演家
新曲
機材
演奏
編曲
著作権
著作隣接権
音楽出版社




メルマガ登録はこちら